書を読みて聖賢を見ざれば、鉛槧の傭となる
―読書不見聖賢、為鉛槧傭―
- [原文](菜根譚 前集五十七項)
- 読書不見聖賢、為鉛槧傭。
- [書き下し文]
- 書を読みて聖賢(せいけん)を見ざれば、鉛槧(えんざん)の傭(よう)となる。
- [原文の語訳]
- 書物を読んでも聖賢(聖人や賢人)の心に触れなければ、筆記具や文章の雇われ人にすぎない。
- [解釈]
- 本をただ読み流すだけで著者の意図することを読み取ろうとしなければ、ただ本を読んだだけのことにしかならないということです。
- 本を買って読んでも、後に何も残らないようでは、単なる浪費するだけの「本屋のお客さん」に終わってしまうだけです。何か1箇所でも琴線に触れる一文を得なければお金と時間を費やす意味がありません。
- せっかく参考書や問題集を買っても、それで満足してしまってはもったいないですね。
- 本は琴線に触れる一文に対して自分の考えなどを直接書き込むなどして著者と対話しながら、汚し使い込むことで血肉となるのですが、本に書き込むことには勇気がいるものでなかなかできません。そこが本の奴隷、雇われの身という解釈になると考えます。
- 現在はSNSなどを使って著者と直接交流できる機会も増えています。その点では本を読むだけの一方通行ではなく、筆者との対話も可能な双方向の時代となっていますね。
- チラシやPOP、メニュー表などのフレーズに簡単に踊らされないようにしたいものです。特に「限定品」とか「残り僅か」といった言葉に弱いですから。
- [参考]
- 書を読みて、聖賢を見ざれば、鉛槧の傭となる。 – 竹林乃方丈庵
[中国古典一日一言]
平成27年(2015年)5月1日から平成28年(2016年)4月30日までの今日の一言は「中国古典一日一言」守屋洋(著)から、同月同日の一言をもとに自分なりに追記や解釈して掲載しています。

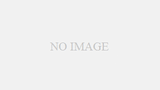
コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています
Syogo Imai liked this on Facebook.
今までたくさんの本を読んで、世間で言われる成功者のお話をたくさん聞いてきました。同じ本を繰り返し読んでも自分の置かれている立場や状況、問題が違うと 同じ本でも受取り方や違う気付きがありますよね。
先駆者達の生きた言葉と自分の行動が今の自分を成長させてきたのだと思います!
Koichi Shimomura liked this on Facebook.
「著者と対話する」読書不見聖賢、為鉛槧傭 書を読みて聖賢を見ざれば、鉛槧の傭となる ―読書不見聖賢、為鉛槧傭― [原文](菜根譚 前集五十七項) 読書不見聖賢、為鉛槧傭。 [書き下し文]… https://t.co/bOZeO0OEzi
舟橋猛 liked this on Facebook.
伊福泰則 liked this on Facebook.
Susumu Yamaguchi liked this on Facebook.
Masakatsu Yamaguchi liked this on Facebook.
松井 よしのり liked this on Facebook.
Kimio Iwata liked this on Facebook.