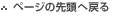なるぱら - [食品新聞]コロナ直撃の外食コーヒー市場で奮闘の富士コーヒー 名古屋喫茶文化に新風「珈琲元年」(2021/8/6掲載) Re: 珈琲元年 鳴子店(2021/7/15開店) - スポットへのコメント - フォーラム
なるぱら - [食品新聞]コロナ直撃の外食コーヒー市場で奮闘の富士コーヒー 名古屋喫茶文化に新風「珈琲元年」(2021/8/6掲載) Re: 珈琲元年 鳴子店(2021/7/15開店) - スポットへのコメント - フォーラム
名古屋市緑区の地域ポータルサイト なるみパラダイス 地域情報発信と情報アーカイブとコミュニティスペース 鳴海・有松・大高・桶狭間・徳重・滝ノ水の地域情報など
当サイトの情報更新は令和4年9月中旬から主にWordpress版で行っています。
[食品新聞]コロナ直撃の外食コーヒー市場で奮闘の富士コーヒー 名古屋喫茶文化に新風「珈琲元年」(2021/8/6掲載) Re: 珈琲元年 鳴子店(2021/7/15開店)
| 対象モジュール | エリアスポット |
| 件名 | 珈琲元年 鳴子店(2021/7/15開店) |
| 要旨 | 令和3年7月15日(木)に珈琲元年 鳴子店が開店します。 ----- 以下、ホームページから引用または抜粋 ----- 富士コーヒー株式会社(本社:愛知県名古屋市、代表取締役社長 :塩澤 彰規)は、「... |
前の投稿
-
次の投稿
|
親投稿
-
子投稿なし
|
投稿日時 2021/8/8 6:28
narupara
 投稿数: 7555
投稿数: 7555
 投稿数: 7555
投稿数: 7555
出店拡大、小売商品にも参入

7月13日、名古屋市緑区の住宅街にある市道沿いに一軒の喫茶店がプレオープンした。その名は「珈琲元年」。1948年に創業し名古屋を拠点にコーヒー焙煎豆の卸売を営む富士コーヒーが2013年に始めたチェーン店名で、店舗数を徐々に拡大している。
この日、プレオープンしたのは6店舗目となる「鳴子店」。招待客が引きも切らさず訪れ店内は活気づき、「珈琲元年」全体にもどことなく勢いを感じさせられた。今後の展開について、16年12月から現職の三代目・塩澤彰規社長に聞くと「今後10年でグループとしては20店舗に拡大していく」と意欲をのぞかせる。
現在、事業の8割を占めるのがコーヒー焙煎豆の卸売販売で約2千の取引先を抱える。将来は、これを徐々に直営とフランチャイズ(FC)で「珈琲元年」の店舗展開にシフトし「半々の割合にしていく」。その根底には喫茶店文化の継承がある。「昨今の個人経営の喫茶店の一番の問題は事業承継。後継者不足の中、なんとかビジネスモデル化して個人だけでなく企業でも運営できるように考えた」と述べる。
「珈琲元年」は、店員がメニューを運んできてくれるフルオペレーションや徹底的にコーヒーにこだわった点などが特徴。フルオペレーションでは、同じく中部エリアをお膝元とする巨大チェーンが席巻している。そうした中で「われわれはコーヒー焙煎業者としてのビジネスモデルを確立していきたい。セルフカフェのチェーン店とも一線を画し、競合よりもワンランク上のフルオペレーションチェーン店を目指していく」。
その際、強みの一つがコーヒーとなる。ハンドドリップやデザインカプチーノ、シングルオリジンなどコーヒーで尖らせる一方で、「あえて高級感を出さず、また効率も追求しない」とする昔ながらのフルサービスの喫茶店を組み合わせて差別化を図っていく。
コーヒーの調達では、世界各国産地とのネットワークを活用。「珈琲元年」で提供されるストレートコーヒーは現在、同社の味覚基準を満たす契約栽培豆「フジスペシャル」「ペルーアチャマル」の2種類を取り揃える。
「フジスペシャル」は、ブラジル最高コーヒー鑑定士に任命された小室博昭氏との出会いにより71年に誕生。以来、産地と同社の間で品質に磨きをかけ「富士コーヒー」の冠をまとった唯一無二のコーヒーに仕立てられている。
一方、「ペルーアチャマル」は生産者・高橋克彦氏の「現地の方々の生活環境を良くしたい」との想いに感銘を受けて同社が独占的に買い付けているコーヒーとなる。
この二つのストレートコーヒーにマンデリンとエチオピア・イルガチェフェをブレンドしたのが「珈琲元年ブレンド」となる。これは「珈琲元年」の店舗のみで提供されるオリジナルブレンドで、これまで一切卸売りされてこなかったが、7月中旬から一部のスーパーで「珈琲元年ブレンド」の小売商品が発売された。
「小売商品は過去にも少しやっていたが、当時は外食・喫茶店がメーンだったためさほど伸ばそうとは思っていなかった。今回、ブランディングの一環として満を持して『珈琲元年ブレンド』を発売し小売商品に改めて参入する」と語る。
「珈琲元年」で唯一効率化を図っているのがフードメニュー。ランチメニューや日替わりメニューをなくし、モーニングに絞り実質“コックレス”にて提供している。
ランチや日替わりメニューをなくし、モーニング一本に。実質“コックレス”で提供する(珈琲元年)
ランチや日替わりメニューをなくし、モーニング一本に。実質“コックレス”で提供する(珈琲元年)
「ランチを提供しない代わりに午後1時までモーニングを展開し、かつボリュームのあるものを提供している。日替わりメニューは、特定のスタッフの技量に左右されやすく属人化の弊害があるため採用していない」と説明する。
前期(21年1月期)の「珈琲元年」の状況は、コロナの影響で4月に底を打ち、6月から徐々に回復しトータルで5%程度の減少にとどめた。
一方、主力の卸売事業は苦戦。「市場環境では中部は東京ほどの落ち込みではないと思うが、当社は長野県にも営業所を持ち、インバウンド需要を失った長野県の落ち込みが一番激しかった」と振り返る。
今期は「珈琲元年」で「鳴子店」に続く新規出店をFC店で2~4店舗見込む。
新規事業としては事業再構築補助金を活用してECサイトを立ち上げる。ECサイトを、挽き売りの直営店「カフェ・セレージャ栄店」と連動させてD2C(ダイレクト・トゥー・コンシューマー)に取り組むことを計画している。
-----
コロナ直撃の外食コーヒー市場で奮闘の富士コーヒー 名古屋喫茶文化に新風「珈琲元年」 - 食品新聞 WEB版(食品新聞社)
https://shokuhin.net/45910/2021/08/06/ryutu/gaishoku/
-----

7月13日、名古屋市緑区の住宅街にある市道沿いに一軒の喫茶店がプレオープンした。その名は「珈琲元年」。1948年に創業し名古屋を拠点にコーヒー焙煎豆の卸売を営む富士コーヒーが2013年に始めたチェーン店名で、店舗数を徐々に拡大している。
この日、プレオープンしたのは6店舗目となる「鳴子店」。招待客が引きも切らさず訪れ店内は活気づき、「珈琲元年」全体にもどことなく勢いを感じさせられた。今後の展開について、16年12月から現職の三代目・塩澤彰規社長に聞くと「今後10年でグループとしては20店舗に拡大していく」と意欲をのぞかせる。
現在、事業の8割を占めるのがコーヒー焙煎豆の卸売販売で約2千の取引先を抱える。将来は、これを徐々に直営とフランチャイズ(FC)で「珈琲元年」の店舗展開にシフトし「半々の割合にしていく」。その根底には喫茶店文化の継承がある。「昨今の個人経営の喫茶店の一番の問題は事業承継。後継者不足の中、なんとかビジネスモデル化して個人だけでなく企業でも運営できるように考えた」と述べる。
「珈琲元年」は、店員がメニューを運んできてくれるフルオペレーションや徹底的にコーヒーにこだわった点などが特徴。フルオペレーションでは、同じく中部エリアをお膝元とする巨大チェーンが席巻している。そうした中で「われわれはコーヒー焙煎業者としてのビジネスモデルを確立していきたい。セルフカフェのチェーン店とも一線を画し、競合よりもワンランク上のフルオペレーションチェーン店を目指していく」。
その際、強みの一つがコーヒーとなる。ハンドドリップやデザインカプチーノ、シングルオリジンなどコーヒーで尖らせる一方で、「あえて高級感を出さず、また効率も追求しない」とする昔ながらのフルサービスの喫茶店を組み合わせて差別化を図っていく。
コーヒーの調達では、世界各国産地とのネットワークを活用。「珈琲元年」で提供されるストレートコーヒーは現在、同社の味覚基準を満たす契約栽培豆「フジスペシャル」「ペルーアチャマル」の2種類を取り揃える。
「フジスペシャル」は、ブラジル最高コーヒー鑑定士に任命された小室博昭氏との出会いにより71年に誕生。以来、産地と同社の間で品質に磨きをかけ「富士コーヒー」の冠をまとった唯一無二のコーヒーに仕立てられている。
一方、「ペルーアチャマル」は生産者・高橋克彦氏の「現地の方々の生活環境を良くしたい」との想いに感銘を受けて同社が独占的に買い付けているコーヒーとなる。
この二つのストレートコーヒーにマンデリンとエチオピア・イルガチェフェをブレンドしたのが「珈琲元年ブレンド」となる。これは「珈琲元年」の店舗のみで提供されるオリジナルブレンドで、これまで一切卸売りされてこなかったが、7月中旬から一部のスーパーで「珈琲元年ブレンド」の小売商品が発売された。
「小売商品は過去にも少しやっていたが、当時は外食・喫茶店がメーンだったためさほど伸ばそうとは思っていなかった。今回、ブランディングの一環として満を持して『珈琲元年ブレンド』を発売し小売商品に改めて参入する」と語る。
「珈琲元年」で唯一効率化を図っているのがフードメニュー。ランチメニューや日替わりメニューをなくし、モーニングに絞り実質“コックレス”にて提供している。
ランチや日替わりメニューをなくし、モーニング一本に。実質“コックレス”で提供する(珈琲元年)
ランチや日替わりメニューをなくし、モーニング一本に。実質“コックレス”で提供する(珈琲元年)
「ランチを提供しない代わりに午後1時までモーニングを展開し、かつボリュームのあるものを提供している。日替わりメニューは、特定のスタッフの技量に左右されやすく属人化の弊害があるため採用していない」と説明する。
前期(21年1月期)の「珈琲元年」の状況は、コロナの影響で4月に底を打ち、6月から徐々に回復しトータルで5%程度の減少にとどめた。
一方、主力の卸売事業は苦戦。「市場環境では中部は東京ほどの落ち込みではないと思うが、当社は長野県にも営業所を持ち、インバウンド需要を失った長野県の落ち込みが一番激しかった」と振り返る。
今期は「珈琲元年」で「鳴子店」に続く新規出店をFC店で2~4店舗見込む。
新規事業としては事業再構築補助金を活用してECサイトを立ち上げる。ECサイトを、挽き売りの直営店「カフェ・セレージャ栄店」と連動させてD2C(ダイレクト・トゥー・コンシューマー)に取り組むことを計画している。
-----
コロナ直撃の外食コーヒー市場で奮闘の富士コーヒー 名古屋喫茶文化に新風「珈琲元年」 - 食品新聞 WEB版(食品新聞社)
https://shokuhin.net/45910/2021/08/06/ryutu/gaishoku/
-----
投票数:45
平均点:4.89
投稿ツリー
-
 [食品新聞]コロナ直撃の外食コーヒー市場で奮闘の富士コーヒー 名古屋喫茶文化に新風「珈琲元年」(2021/8/6掲載) Re: 珈琲元年 鳴子店(2021/7/15開店)
(narupara, 2021/8/8 6:28)
[食品新聞]コロナ直撃の外食コーヒー市場で奮闘の富士コーヒー 名古屋喫茶文化に新風「珈琲元年」(2021/8/6掲載) Re: 珈琲元年 鳴子店(2021/7/15開店)
(narupara, 2021/8/8 6:28)