過ぎたるは猶及ばざるが如し
―過猶不及―
- [原文](論語 先進第十一)
- 子貢問。師與商也孰賢。子曰。師也過。商也不及。曰。然則師愈與。子曰。過猶不及。
- [書き下し文]
- 子貢問う、師と商と孰れか賢れる。子曰く、師や過ぎたり。商や及ばず。曰く、然らば則ち師愈れるか。子曰く、過ぎたるは猶お及ばざるが如し。
- [原文の語訳]
- 子貢がたずねた。師(し)と商(しょう)とでは、どちらがまさっているのでしょうか。孔子が言う。師は行き過ぎている。商は行き足りない。子貢が更にたずねた。では、師の方がまさっているのでしょうか。すると、孔子が言う。行き過ぎるのは行き足りないのと同じだ。
- [解釈]
- ゆき過ぎはやり足りないのと同様。
- 最近の「○○過ぎる△△」というメディアの表現を自分が批判しているのはこの一言を根本にしているからです。
- 過不足なくバランスのとれた人が理想的です
- 無責任過ぎても責任感が強すぎても自他に負担がかかるのです。
- 一生懸命に取り組みすぎるのも体によくありません、限度をわきまえるようにしましょう。
- 戦の時代も勝ちに乗じて追撃しすぎ、反攻されるということが多くあったようです。
- 「大弁は訥なるが如し」「久しく尊名を受くるは不詳なり」なども過ぎたる失敗に対する注意喚起です。
- 一昔前の情報不足だった頃も、今の情報化社会となっても情報過多で結局正確な判断が難しいままなのです。
- サプリメントもあくまで補助食品ですし、薬も過ぎれば毒となります。お酒もほどほどに。
- 徳川家康も家訓遺訓の中で「及ばざるは過ぎたるに勝れり」と語っています。
- [参考]
[中国古典一日一言]
今日の一言は「中国古典一日一言」守屋洋(著)から、同月同日の一言をもとに自分なりに追記や解釈して掲載しています。

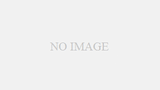
コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています
[ブログ]「何事も過不足なくバランスよく」過猶不及 http://t.co/OH0zFUPKed
Issey Yamamoto liked this on Facebook.
Koichi Shimomura liked this on Facebook.
Susumu Yamaguchi liked this on Facebook.
Katshiro Noguchi liked this on Facebook.
舟橋猛 liked this on Facebook.
Kimio Iwata liked this on Facebook.
宿澤直正 liked this on Facebook.
Nobuyuki Katsuda liked this on Facebook.
松本 まもる liked this on Facebook.
Mitsuko Ohmura liked this on Facebook.