言は行を顧(かえり)み、行は言を顧む
―言顧行、行顧言―
- [原文](中庸)
- 庸徳之行、庸言之謹、有所不足、不敢不勉、有余不敢尽、言顧行、行顧言、君子胡不造造爾。
- [書き下し文]
- 庸徳(ようとく)をこれ行い、庸言(ようげん)をこれ謹み、足らざる所あれば、敢えて勉めずんばあらず、余りあれば敢えて尽くさず、言は行いを顧み(かえりみ)、行いは言を顧みる、君子胡ぞ(なんぞ)造造爾(ぞうぞうじ)たらざらん。
- [解釈]
- 原文の語訳としては
君子とは日常的な徳を実践して、日常的な言葉を謹み、徳に及ばない所があれば、それを補おうとして必ず努力するものである。言葉が過剰であれば敢えて言い尽くさず、言葉は自分の行いを振り返ってから話し、行動は自分の言葉を振り返ってから行う、そのような君子がどうして篤実・誠実ではないなどと言えるだろうか。 - 話をするときは自分のことを棚に上げていないか、大風呂敷を広げていたり、話が飛躍過ぎていないか、常に意識するようにすれば、余計なことは言えなくなる。
- 経験談や経験知は人に話しても説得力がある。
- 人に言う前に自分はきちんとやっているか?その行動は言ったことと食い違ってないか?言動が矛盾していては説得力もなければ信用も得られない。→言行一致
- 目先の利益を得ようがために自分のキャパを超えて「やりますやります」と安請け合いして、後から悲鳴を上げていては信用も得られない。
- [参考]
- 『中庸』の書き下し文と現代語訳:11
[中国古典一日一言]
今日の一言は「中国古典一日一言」守屋洋(著)から、同月同日の一言をもとに自分なりに追記や解釈して掲載しています。

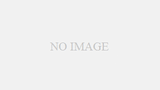
コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています