糟糠の妻は堂より下さず
―糟糠之妻不下堂―
- [原文](後漢書)
- 弘曰、臣聞貧賤之知不可忘、糟糠之妻不下堂。
- [書き下し文]
- 弘曰く、臣聞く、貧賤(ひんせん)の知は忘る可(べ)からず、糟糠(そうこう)の妻は堂より下さず、と。
- [原文の語訳]
- 宋弘が言う。私は「貧餞の交わりは忘るべからず(貧しく地位が低かった頃の友達はいつまでも忘れてはならない)、糟糠の妻は堂より下さず(苦労を共に下妻は家から追い出してはならない)と聞いています。
- [解釈]
- 貧しい頃から苦労を共にしてきた妻は、立身出世ののちも離縁するわけにはいかない。
- 皇帝の姉が未亡人となったので、皇帝は再婚相手を探していたところと宋弘という人物の評判が良い。そこで呼び出して謎掛けをした。「宋弘よ、地位が上がったならば、相応の友人に代えるものだし、裕福になったならば妻もふさわしい人物に代えるものだと聞くが、そんなものか?」すると宋弘は「苦労を共にした妻を追い出してはならないと聞いています」と応え、それを聞いた皇帝は説得するのは無理だと断念したそうです。
- 芸能界では売れる前に一般人と結婚していたけど、売れ出したら離婚、芸能人相手に再婚するというケースが「反する例」に相当するのかもしれません。
- 論語に「己に如かざる者を友とするなかれ(善を求め道を修め、みずからを向上させるためには、自分より劣る者と交わってはならない。)」(学而篇)という言葉がありますが、レベルアップのために交友関係を広げる一方で、いつしか傲慢になった自分を初心に帰らせるためには、苦労をともにした人が必要だと考えます。
- 地位が向上してから危機に遭遇した時、内助の功を果たしてくれるのは、昔どこで何に苦労し、それをどうやってクリアしたか経験知をもってくれている、当時すぐ側にいてくれた人だけです。
- 一方、苦労させられた旦那に愛想をつかした奥さんはというとこうはいかないですよね。旦那さんの退職を機に三行半を突きつけて、残りの人生を謳歌したいからと熟年離婚なんてことが現代は多いようですし。
- 相棒という言い方に置き換えると、道具を大事に使うのも同じではないでしょうか。職人として腕を上げていくうちに、長く同じ道具を使い続けていると、時に周りから「そろそろ新しいものに買い換えたらどうか?」と言われることも。でも「いやこれが手にしっくり馴染んでいいんだよ」と返す姿が重なるような気がします。
- [参考]
- 宋弘 – Wikipedi
[中国古典一日一言]
今日の一言は「中国古典一日一言」守屋洋(著)から、同月同日の一言をもとに自分なりに追記や解釈して掲載しています。

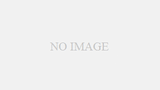
コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています
[ブログ]「苦労を共にした相棒とはいつまでも一緒に」糟糠之妻不下堂 http://t.co/H8dP8J2NUg
Susumu Yamaguchi liked this on Facebook.
Masako Satou liked this on Facebook.
Koichi Shimomura liked this on Facebook.
Kimio Iwata liked this on Facebook.
Masakatsu Yamaguchi liked this on Facebook.
Kazuma Yamada liked this on Facebook.
Katshiro Noguchi liked this on Facebook.
松本 まもる liked this on Facebook.
舟橋猛 liked this on Facebook.
Hiroshi Kato liked this on Facebook.