初めあらざること靡く、克く終わりあること鮮なし
―靡不有初、鮮克有終―
- [原文](詩経 大雅 蕩)
- 靡不有初、鮮克有終。
- [書き下し文]
- 初めあらざること靡(な)く、克(よ)く終わりあること鮮(すく)なし。
- [原文の語訳]
- 初めがないものはないが、完成した終わりは少ない。
- [解釈]
- 最後までやり遂げられることは少ないということです。
- 誰しも事のし始めは盛大であっても、その勢いを持続して完遂できる人は少ないものです。「はじめの勢いはどこへ行った」などとはよく言ったものです。
- 数年に一度の人材として華々しく登場し、そして有終の美を飾るところで活躍できる人は稀です。
- できる人は「初志貫徹」であったり、力を出しきらずに八分の力を持続させていくのです。
- ネットのサービスでも開始時はテレビなどで頻繁にCMを流しますが、下火になるとさっさとサービス自体を終了させてしまうケースが見受けられます。損切りといってしまえばそうかもしれませんが、利用者はたまったもんじゃないですね。
- 一時期政権を奪取した政党がまさに体現していたのではないでしょうか。
- 大きな花火を打ち上げておきながら残り火も消えないうちに部下に押し付け、成果が出なければ責任転嫁するようなトップには困りものです。
- [参考]
[中国古典一日一言]
今日の一言は「中国古典一日一言」守屋洋(著)から、同月同日の一言をもとに自分なりに追記や解釈して掲載しています。

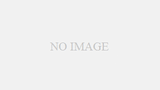
コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています
耳の痛い話です。
もう20年以上も前の話ですが、大学院の修士論文を指導教官に見せたところ、「竜頭蛇尾」だねと言われたのを思い出します。
ガ━(゚Д゚;)━ ン !!!
とりあえず修士論文という形で終わりを作らなければならなかったのですが、本当のところ、研究として「未完成」だったからなのでしょう。
最初のテンションを持続し続けるのは大変ですよね。イベントなどのマンネリ化もそうですよね。自分も中途半端が多いので耳が痛いです(^^;
根性のない私は、マラソンでいうと、スタートして10分もしないうちに、持続力が切れてしまいます。(^.^;
Naoto Yamagami liked this on Facebook.
伊福泰則 liked this on Facebook.
鈴木晃子 liked this on Facebook.
Kimio Iwata liked this on Facebook.
Susumu Yamaguchi liked this on Facebook.
佐橋亜子 liked this on Facebook.
CoinLaundry Rapport liked this on Facebook.
Yamakawa Tsurugi liked this on Facebook.
Koichi Shimomura liked this on Facebook.