その本乱れて末治まる者はあらず
―其本亂而末治者否矣―
- [原文](大学)
- 其本亂而末治者否矣。
- [書き下し文]
- その本乱れて末治まる者はあらず。
- [原文の語訳]
- その大本の修身が乱れているのに、世の中が治まっているという例はいまだ無い。。
- [解釈]
- 根本が乱れているのに全体がまとまるということはあり得いないということです。
- 基本ができていないと何事も修まりはよくありませんね。本を立てれば末おのずから立つということです。
- 人にお願いや指摘する前に「まず自らやってみせる」にも通じるところがあるのではないでしょうか。
- 一人ひとりのマナーが悪かったり、悪しき心が強くなって犯罪を犯すようになると、それを規制するためのルールや法律を作らなければいけなくなります。無法地帯は治まりきれてない典型例ですね。皆の心が修まって平穏無事であれば法律などは本来無用な長物となるのです。
- できる人は自ら修身することで周りを自然と感化させ組織全体の品性を向上させるのです。
- 好き勝手なトップのもとでは組織が統率されるわけがありません。
- 失敗したときでも、それを省察することも正すこともせず、そのままにしておけば同じ過ちを繰り返すことになるのです。
- [参考]
- 『大学』の書き下し文と現代語訳:7
[中国古典一日一言]
平成27年(2015年)5月1日から平成28年(2016年)4月30日までの今日の一言は「中国古典一日一言」守屋洋(著)から、同月同日の一言をもとに自分なりに追記や解釈して掲載しています。

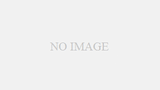
コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています
Syogo Imai liked this on Facebook.
伊福泰則 liked this on Facebook.
Koichi Shimomura liked this on Facebook.
Kimio Iwata liked this on Facebook.
Kenji Obata liked this on Facebook.
Susumu Yamaguchi liked this on Facebook.
Kaname Kojima liked this on Facebook.
舟橋猛 liked this on Facebook.