一臠の肉を嘗めて、一鑊の味を知る
―嘗一臠肉、知一鑊味―
- [原文](淮南子 説山訓)
- 嘗一臠肉、知一鑊味。
- [書き下し文]
- 一臠(いちれん)の肉を嘗めて、一鑊(いっかく)の味を知る。
- [原文の語訳]
- ひときれの肉を味わってみて、肉鍋全体の味を知る。
- [解釈]
- 味見をして全体を確かめるということから、一部分をもって全部を察知するということです。
- 「一を聞いて十を知る」という言葉もありますね。大局観を持ち合わせたり、全体像がイメージできる人はわずかな情報からでも全体を把握ことができそうです。
- 本を選ぶときに、パラパラと数ページを読んで買うかどうかを判断するのもそんな感じでしょうか。また「はじめに」「さいごに」や冒頭を読むことで判断する人も多いようですから、そこを疎かにしてはいけません。
- 話す側、伝える側は「つかみ」を大事にしなくてはいけないですね。
- 組織やグループ内の一部の人の言動を見て、その人が属する全体がそうであるかと判断するのは難しいですが、できる人はそれを加味した上で、全体を把握することができるのです。
- とりあえずやってみることで、結果が予想しやすくなるものです。机上の空論ではなかなか事は進みません。
- 「食べず嫌い」には、ならないようにしたいものです。
- [参考]
- 吉屋信子を批判した小林秀雄――「わが友の生涯」(今日出海)より
[中国古典一日一言]
平成27年(2015年)5月1日から平成28年(2016年)4月30日までの今日の一言は「中国古典一日一言」守屋洋(著)から、同月同日の一言をもとに自分なりに追記や解釈して掲載しています。

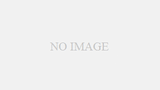
コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています
伊福泰則 liked this on Facebook.
「味見して全体を把握する」嘗一臠肉、知一鑊味 一臠の肉を嘗めて、一鑊の味を知る ―嘗一臠肉、知一鑊味― [原文](淮南子 説山訓) 嘗一臠肉、知一鑊味。 [書き下し文]… https://t.co/24rIZ2Mi97
お店にとっては 第一印象やオススメメニュー、日替わりランチのような間口の広いもので判断されやすそうですね。
そういえばご飯屋では「ご飯を食べれば分かる」ともいいますよね。中華料理だとチャーハンで実力がわかるといいますし。
Kaname Kojima liked this on Facebook.
Masako Satou liked this on Facebook.
Kenji Obata liked this on Facebook.
Susumu Yamaguchi liked this on Facebook.
舟橋猛 liked this on Facebook.
Koichi Shimomura liked this on Facebook.
Syogo Imai liked this on Facebook.
Kenichiro Ota liked this on Facebook.
Kimio Iwata liked this on Facebook.
Hiroki Hisanaga liked this on Facebook.
Kouichi Yasuda liked this on Facebook.
Masakatsu Yamaguchi liked this on Facebook.