善く問いを待つ者は鐘を撞くが如し
―善待問者如撞鐘―
- [原文](礼記 学記第十八)
- 善待問者如撞鐘。
- [書き下し文]
- 善く問いを待つ者は鐘を撞(つ)くが如し。
- [原文の語訳]
- 善く問いを待つ者(立派な教師)は鐘を撞く(教えを受ける方の)叩き方いかんで、大きくも鳴れば、小さくも鳴る。
- [解釈]
- 質問に応えるのがうまい教師は、まるで撞かれた鐘のようなもので、弱く撞けば小さく鳴り、力強く撞けば大きく鳴る。誰にでも単一的に応えるのではなく、鐘の鳴り方ように応じる。
- 一文は教える側に立った書き方ですが、実際は教えを請う側になる方が多いと思います。そういった時は、学ぼうという姿勢がなければ吸収もできない。学習意欲が大きければそれだけ吸収力も大きくなります。比例するということです。
- またどうせ撞くならば、より響きの良い鐘の方が良いでしょう。孔子は「安易に自分より知徳の劣った人と交って(反面教師にでもできるが)いい気になるのはよくないことだ」と、レベルの上の人とつきあうべきだ勧めています。良い物に触れないと良し悪しの判断はできません。
- 政治の世界でも議員のレベルに応じた対応を官僚はする言われます。鋭い質問や厳しい追求なのか、表面的な重箱の隅をつつく程度の内容なのかによって、出してくる回答が違ってくるそうです。ここでも議員の質がモノを言うわけです。
- 質問を投げたことで、受けた側が「なるほど、そういう観点があったか」とか「簡単に答えるわけにはいかないから自分もさらに学習しなくては」という意識があれば、互いの向上にもつながっていくでしょう。
- 孔子も論語なかで複数の弟子から同じような質問を受けながら、弟子の性格や状況に応じて違う返答をしていますし、毛利元就も家来に対し同じような対応をしていたそうです。
- 「打てば響く」と言われる人になりたいですね。
- [参考]
- 善く問いを待つ者は鐘を撞くが如し:原文・書き下し文・意解 言葉の散歩道102 | ナオンの言葉の散歩道
[中国古典一日一言]
今日の一言は「中国古典一日一言」守屋洋(著)から、同月同日の一言をもとに自分なりに追記や解釈して掲載しています。

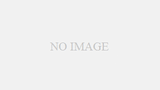
コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています
[ブログ]「鐘の鳴リ方は撞き方しだい」善待問者如撞鐘 http://t.co/xYlhGlmNmY
Issey Yamamoto liked this on Facebook.
Koichi Shimomura liked this on Facebook.
Kimio Iwata liked this on Facebook.
kawai shinichiro liked this on Facebook.
Hiroshi Kato liked this on Facebook.
Susumu Yamaguchi liked this on Facebook.
舟橋猛 liked this on Facebook.
Kazuhide Fujita liked this on Facebook.