国土交通省が信号機のない円形の交差点「ラウンドアバウト」の検討会を設置し検証を開始したそうです。
まず、ラウンドアバウトの定義として以下の4つの条件を満たした交差点をさすとのことです。

Squashed Car / dorofofoto
- 3本以上の道が接続されている交差点の中心に、円形の島がある構造であって、その島の周りを回るように通行する。
- 円形の島の周りを回る環流路に交通優先権があり、環流路に流入する車は必ず一旦停止をする
- 回転方向が一定であり逆転ができない
- 信号は無い。
強味と弱味がそれぞれあるようです。
最上部の条件を満たしたものは、一般的に「ロータリー式交差点」と呼ばれていて国内では多く存在していますね。
国土交通省は4日、信号機のない円形の交差点「ラウンドアバウト」について有識者検討会を設置し、導入に向けて課題などの検証を始めた。
ラウンドアバウトは交差点内を時計回りの一方通行にする仕組みで、環状部分を走る車両の通行を優先し、環状部分を抜ける際は左折する。進入する際、減速や一時停止をする必要があるため、事故抑止につながると期待されている。信号機が不要になるため、震災時の停電でも影響を受けないなどの利点もある。欧米では広く普及しており、国内では長野県飯田市などに設置例がある。
一方、環状部分に進入できる車両の数には限界があるため、交通量の多い場所での設置は難しいという指摘もある。4日に開かれた検討会の初会合では、ラウンドアバウト導入による海外の事故減少率、国内で行われた社会実験の結果などが報告された。
自分が感じたところだと円形になり緩やかになる分、通常の交差点よりも面積を必要とする可能性があり、すでに都心部など建物が密集している所では難しそうです。
かといって地下で作るのは逆に危険性が増しそうなのは想像に難しくないです。
なので、郊外でこれから都市開発をするところか、道路の規模の割に広い交差点のところくらいでしか整備は難しいかと。
そういえば名古屋駅前もロータリー式交差点になっています。
で「ひょっとして」と思って古い写真をググってみたら、昭和中期のものでは車も少なくて信号もついてない感じ。
ということである意味「原点回帰」ということになるのでしょうか。
でも今は交通量が圧倒的に違いますからね。
[参考ページ]
昭和中期の名古屋駅前ロータリーの写真を掲載されています。
さようなら 大名古屋ビルヂング | 吾が徒然 – 楽天ブログ
第1回 ラウンドアバウト検討委員会開催のお知らせ
報道発表資料:第1回 ラウンドアバウト検討委員会の開催について – 国土交通省
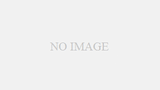
コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています