術あれば則ち人を制し、術なければ則ち人に制せられる
―有術則制人、無術則制於人―
- [原文](淮南子)
- 有術則制人、無術則制於人。
- [書き下し文]
- 術あれば則ち人を制し、術なければ則ち人に制せられる。
- [原文の語訳]
- 術があれば人を動かすことができ、術がなければ人に動かされる。
- [解釈]
- 人心を掌握する術を持たないと人を動かすことはできないということですが、その方法は人それぞれですよね。根回しを充分に行うタイプや無言実行、やって見せるなど多彩です。逆に持ち合わせていないと、受け身でしか行動ができなくなってしまいます。
- これは組織だけでなく、交渉の場でも言えることではないでしょうか。主導権を握るにはこちらが相手を動かさないといけません。それは積極的に先行するのか、一旦相手を受け止めてからなのかはその人次第でしょう。
- たとえ仕事ができる人でも、人間関係の構築が不得手だと、仕事がロクにできないけど結局は要領のいい人に使われてしまうでしょう。
- できる人は、その術を露見させず上手に使いこなすのです。
- [参考]
- 淮南子|3分でよめる中国古典ブログ
[中国古典一日一言]
今日の一言は「中国古典一日一言」守屋洋(著)から、同月同日の一言をもとに自分なりに追記や解釈して掲載しています。

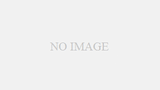
コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています
Koichi Shimomura liked this on Facebook.
Kimio Iwata liked this on Facebook.
伊福泰則 liked this on Facebook.
舟橋猛 liked this on Facebook.
Susumu Yamaguchi liked this on Facebook.
鈴木晃子 liked this on Facebook.
Kouichi Yasuda liked this on Facebook.