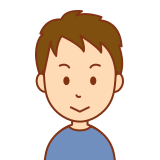
大高城跡(緑区)発掘調査の現地説明会が令和5年2月18日(土)に開催され、名古屋市教育委員会の調査で本丸を囲む大規堀の存在と形状が裏付けられたことが報告されたそうです。
信長の大高城攻め 堀で対抗
市教委、発掘調査説明会 形状も裏付け市教委が進める国史跡大高城跡(緑区)発掘調査の現地説明会が十八日に開かれた。二〇二年度からの調査で、本丸を囲む大規堀の存在と形状が裏付けられたことが報告された。
大高城は十六世紀初頭までに造られたとみられる平山城で、桶狭間の戦い (一五六〇年)の際に、今川義元配下の松平元康(徳川家康)が兵糧を運び入れたことで知られる。江戸初期の絵図に堀などの構造が記されているが、現状は平地のため、市教委文化財保護室を中心に調査を始めた。
二度のレーザー探査で遺構の位置を推定。 昨年一~三月の発掘調査で、幅一四・八が以上、最大深さ四以上の堀があったことが確認された。今年一月の調査で、堀の底が平らな「箱堀」とV字状の「薬研堀」を組み合わせた形であることも判明した。
堀北側の本丸部分には硬い整地層が見つかり、築城時に堀の掘削で出た土を使整地したとみられることも分かった。本丸南側では弥生時代や中世の土器が見つかり、築城の前から人この地を利用していたことも推定された。
桶狭間の戦いで、織田信長は大高城を包囲して兵糧攻めにしたと伝えられる。市教委によると、奈良大の千田嘉博教授(城郭考古学)は今回の調査結果について、「今川軍が本丸の周りに堀を巡らせ、守り特に強化しなければならないほど、信長が激しく攻めて城を追い詰めたの初めて明らかにした画期的な成果」と評価している。市教委は二三年度以降も測量などを進め、城跡公園の園路整備や案内板設置などの保存活用計画づくりを進める。 (芝野享平)
市教委、発掘調査説明会 形状も裏付け市教委が進める国史跡大高城跡(緑区)発掘調査の現地説明会が十八日に開かれた。二〇二年度からの調査で、本丸を囲む大規堀の存在と形状が裏付けられたことが報告された。
大高城は十六世紀初頭までに造られたとみられる平山城で、桶狭間の戦い (一五六〇年)の際に、今川義元配下の松平元康(徳川家康)が兵糧を運び入れたことで知られる。江戸初期の絵図に堀などの構造が記されているが、現状は平地のため、市教委文化財保護室を中心に調査を始めた。
二度のレーザー探査で遺構の位置を推定。 昨年一~三月の発掘調査で、幅一四・八が以上、最大深さ四以上の堀があったことが確認された。今年一月の調査で、堀の底が平らな「箱堀」とV字状の「薬研堀」を組み合わせた形であることも判明した。
堀北側の本丸部分には硬い整地層が見つかり、築城時に堀の掘削で出た土を使整地したとみられることも分かった。本丸南側では弥生時代や中世の土器が見つかり、築城の前から人この地を利用していたことも推定された。
桶狭間の戦いで、織田信長は大高城を包囲して兵糧攻めにしたと伝えられる。市教委によると、奈良大の千田嘉博教授(城郭考古学)は今回の調査結果について、「今川軍が本丸の周りに堀を巡らせ、守り特に強化しなければならないほど、信長が激しく攻めて城を追い詰めたの初めて明らかにした画期的な成果」と評価している。市教委は二三年度以降も測量などを進め、城跡公園の園路整備や案内板設置などの保存活用計画づくりを進める。 (芝野享平)




コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています