大高城の発掘調査で戦国時代の遺物が見つかり、城の歴史が裏付けられました。この城は桶狭間の戦い前夜、松平元康(後の徳川家康)が包囲をかいくぐり「兵糧入れ」として使った場所として知られています。城跡は1938年に国史跡に指定され、現在は公園となっています。この出土物とともに発掘成果を28、29日の両日にイオンモール大高でパネル展示されます。城の歴史がより身近に感じられる機会です。

大高城跡から戦国の土器
市の発掘調査で出土
きょう、あす展示 「絵図や記録での存在に臨場感」
織田信長が今川義元を破った桶狭間の戦い(1560年)の舞台の一つ、大高城の跡地(緑区大高町城山)で市が実施した発掘調査で、戦国時代に使われていた土器や刀の装具が見つかった。この場所に城館が存在したことを考古学的にも裏付けた形で、28、29日の両日、地元のイオンモール大高(同区南大高2)で出土物8点とともに発掘成果をパネル展示する。
大高城は桶狭間の戦いの決戦前夜、今川方だった松平元康(のちの徳川家康)が織田方の包囲をかいくぐって「兵糧入れ」に成功した城として知られる。江戸時代初期に尾張藩が作った絵図に、大規模な堀を備え城跡として記録されているが、その時点で既に廃城となっており、詳細は分かっていなかった。
城跡は1938年に国史跡に指定され、現在は公園になっているが、市教委が2022~23年に初めて発掘調査を実施。幅約55、深さ4以上に及ぶ堀の跡を確認した。 堀を埋めてい土からは、15世紀後半~16世紀前半のものと考えられる茶わんやとっくりの破片など数百点以上が見つかった。
すずりで墨をする際に使う小さな水差しや、日本刀のさやに収める銅製の小道具「笄」も出土した。水差しは領主などが文書を書く際に、笄は武士が髪の毛など身だしなみを整えるために使われたと考えられ、桶狭間の戦い以前にこの地を治めた豪族の花井氏や水野氏といった勢力が使用していた可能性があるという。
イオンモール大高の専門店街2階で、両日とも午前10時~午後4時に展示する。調査を担当市教委文化財保護室の学芸員、岡千明さんは「絵図や記録の中での存在だった大高城が、より臨場感を持って感じ取れる出土物だと思う。 この機会に間近で見てほしい」と来場を呼びかけた。(安藤孝憲)
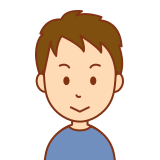




コメント受付中です どなたでもコメントできますがスパム対策を施しています